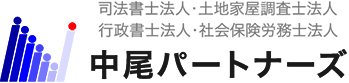遺言とは? Will
遺言とは?
しかし、死んでしまった後ではどうでしょうか?
ご自身の意思とは関係なく、ご自身の財産が分配されてしまう可能性が出てきますし、不本意に、その財産が相続問題の火種になることさえあります。
ご自身の財産について、自分自身の意思を尊重・反映した分配を行う。これが「遺言」です。
遺言書を見つけたら
検認手続とは
【注意点】
遺言の種類
1.自筆証書遺言
-
全文を自筆で書かなければならない
用紙の種類、大きさ、筆記用具に決まりはありませんが、鉛筆など簡単に消せるものは避けたほうが良いでしょう。手軽さでいえば、パソコンやワープロを使いたいところですが、これは自筆でなくなるために認められません。また、自筆をコピーしたものも認められません。
※ 法改正により、財産目録等につき、一部自筆以外の作成が認められました。詳しくは、本WEBサイト変わる遺言をご一読ください。 -
日付を明記しなければならない
遺言を書いた日付を明記しなければなりません。「◯月」や、「◯月吉日」という書き方なども、明確な日付を特定できないため認められません。
-
署名や押印をしなければならない
遺言書には、自らの署名と印鑑による押印が必要になります。印鑑は認印であっても構いませんが、実印が好ましいでしょう。
さらに、
-
亡くなった際に遺言書が発見されない可能性がある
-
詐欺・脅迫・紛失・偽造・変造の可能性がある
-
家庭裁判所の検認が必要になる
2.公正証書遺言
-
証人2名以上の同席が必要
公正証書遺言には、必ず2名以上の証人が必要となります。証人は“誰でも良い”というものではなく、相続人などは証人になることができないなど、要件があります。自筆証書遺言と違い、遺言内容を秘密にすることもできません。
-
費用がかかる
公証人に払う費用が発生します。財産が多くなればその費用も高額になります。
3.秘密証書遺言
自筆である必要がない、封をするので偽造の危険がないなどのメリットはありますが、手続きは公正証書遺言同様に費用や手間が掛かる上、自筆遺言証書同様、その遺言書が無効になる可能性もあり、実際に利用されている人は少ないのが実情です。
理由としては、公正証書遺言は公証人に対する費用が掛かるなどの注意点はありますが、専門家が作成する遺言書は無効になることは考えられず、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認作業が不要になります。
さらに、作成された公正証書遺言は公文書として強力な証拠力を有しており、その原本は公証役場で保管されます。
加えて、遺産分割協議をすることなく、直ちに公正証書遺言に基づいた遺産分配が行えます。
このようにメリットとデメリットを総合的に考慮して、公正証書遺言をおすすめします。
遺贈について
「相続」との決定的な違いは、相続の場合、何ら手続きを経ることなく、当然に被相続人の財産が相続人に引き継がれることをいいますが、「遺贈」の場合には当然に発生するものではなく、遺言書に従って与えられるものであることです。
また、「遺贈」と「贈与」も似ていますが、これも異なるものです。
「贈与」の場合には、贈る側と贈られる側(=貰う側)の合意によって成り立つ、いわば契約であるのに対し、「遺贈」は贈る側(いわゆる遺言者)の一方的な行為となります。そのため、「遺贈」の場合、贈られる側は「遺贈の放棄」をすることが出来ます。
「遺贈」の場合、遺言者を「遺贈者」、遺贈により利益を受ける者を「受遺者」と呼びます。
「遺贈」は「相続」とは違い、誰に対しても自由に行うことが出来ます。相続権のない個人でも、法人や団体でも行うことが出来ます。
「遺贈」には数種類があり、詳しく説明します。
1.包括遺贈
例)相続財産の全部とか、相続財産の◯%、相続財産の◯割など
特定の財産を示さず、割合で決めたものを包括遺贈といいます。ここで注意しなければならないのは、包括遺贈を受けた割合に応じて、同じだけの債務も負担しなければなりません。
2.特定遺贈
例)◯◯会社の株、◯◯市◯◯町◯番の土地など
特定遺贈は目的物を指定することになります。包括遺贈とは違い、遺言書で特定の指定がない限り、債務を引き継ぐことはありません。
3.条件付遺贈
4.始期付遺贈
5.負担付遺贈
遺留分
遺留分について
相続人がこの内容に納得していたら問題ありません。遺言内容どおりに財産は分配されます。しかし、遺言者の財産に頼って生活していた相続人がいる場合、財産をもらえないと困ってしまいます。
そこで法律は、遺言者の身近な親族である一定の相続人に対して、今後の生活を保障するために、亡くなった方の相続財産のうち、最低限の相続分を確保する権利を遺留分として認めています。
なお、この遺留分は、亡くなった方が生前におこなった一定の贈与についても及びます。
-
遺留分がある人は?
兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があります。(配偶者、子、父母等の直系尊属※)
-
遺留分の割合は?
相続財産の2分の1です。相続人が数人いる場合は、上記2分の1を更に各相続人の法定相続分の割合で計算します。
※なお、父母などの直系尊属のみが相続人である場合、相続財産の3分の1になります。
遺留分の請求について
なお、遺留分の請求方法は、口頭でも書面でも構いませんが、後日のトラブルを防ぐために書面(内容証明郵便)で行うことをお勧めします。
時効について
また、遺留分の侵害に気づかなかったとしても、相続開始から10年を経過すると請求権は消滅します。